「管理職は罰ゲーム」—そんな言葉を耳にすることが増えました。
確かに、ハラスメントに厳しい時代、管理職はストレスの多い立場と思われがちです。
また「自分の人生を大切にしたい」という価値観を持つ人が増えたことで、あえて出世を目指さない選択をする人も増えています。
しかし、そこに私は異を唱えたい。
実は、やり方やマインドセット次第で、管理職は最強のポジションになれるのです。
なぜなら、組織を動かし、環境をアレンジできる権限を持つのは管理職だけだからです。
ここでは「管理職は罰ゲーム」と言われる理由にすべて反論し、むしろ管理職こそボーナスゲームであることをお伝えします。
読み終えたとき、あなたの管理職への見方は変わっているはずです。
- これから管理職を目指す方は、正しい情報をもとにキャリアを考えるきっかけ
- 現役管理職の方は、今の働き方を見直し、もっとラクに、もっと強くなるヒント
を得られるでしょう。
 TAKA
TAKA私は担当時代より、むしろ管理職になってからの方がストレスが減りました。相性以前に管理職の誤解が多いと感じています。
「管理職は罰ゲーム」と言われる理由
「管理職は罰ゲーム」と言われる背景には、時代の変化とともに生まれた価値観が大きく影響しています。
最近の調査結果などをもとに、多い理由を3つ挙げてみました。
- 管理職に向いていない
- 仕事量や仕事時間が増える
- 責任の重い仕事をしたくない
「管理職になることに興味がない」と回答した方に「管理職になりたくない理由」を伺うと、トップは52%で「管理職に向いていないと思うから」でした。
以下に詳しく見ていきます。
1,管理職に向いていない
この回答には以下のような理由も紐づけられます。
- 出世欲がない
- 金銭欲がない
- 今の職務を続けたい
- 自分の上司に憧れない
ワークライフバランスを重視する生き方により「出世=成功」という価値が薄れつつあります。
人生の充実を仕事以外に求める人が増えているのです。
日本の働き手も、調査史上初めて、就業先の選定において重視する項目として、ワークライフバランス(日本65% 、世界83%)が報酬(日本62%、世界82% )を上回る結果となりました。
またハラスメントの多様化により、人間関係の摩擦に疲弊する上司を目の当たりにして「ああはなりたくない」と感じる人も少なくありません。
2,仕事量や仕事時間が増える
この回答をする人は具体的に以下のようなことを感じているようです。
- 割に合わない
- 給与面での魅力がない
- ストレスを避けたい
仕事量や労働時間が増える一方で、それに見合う報酬やリターンが少ないと感じる人が多いのがこの理由です。
確かに、日本では終身雇用の崩壊が進んだ結果、経験とともに負担が増えても給与が大幅に上がるわけではないという現実があります。
1976年、1995年、2023年の各調査年で、勤続年数が増加するにつれて平均所定内賃金額も上昇しています。しかし、一定の勤続年数を超えると賃金の上昇幅が緩やかになる、もしくは頭打ちになる傾向が見られます。
出典元:労働政策研究・研修機構
そのため、キャリアを重ねることに魅力を感じにくくなっているのです。
3,責任の重い仕事をしたくない
- 割に合わない
- ストレスを避けたい
こちらはより精神的な負担に対しての拒絶です。
昔は「苦労は買ってでもしろ」と言われていましたが、今は「無駄な苦労は避けるべき」いう考えが主流です。
また、企業でも若手社員のメンタルヘルス不調は増えており、無視できない問題になっています。
正社員の14.3%、公務員の16.7%が、過去3年以内に治療なしでは日常生活が困難なほどのメンタルヘルス不調を経験。 若年層ほど経験率が高く、20代男性の18.5%、20代女性の23.3%
そのため、できるだけストレスの少ない生き方や働き方を選ぶ傾向が強くなっているのです。
すべての理由は現代的であり対策が必要な問題ですが、だからと言って「管理職=罰ゲーム」と考えるのはあまりに短絡です。
次章では一つ一つの理由について、勘違いや実際の情報をもとに論破していきます。



管理職予備軍の方だけでなく、現役の管理職の人にもぜひ共感してもらいたい!
「管理職は罰ゲーム」を完全論破
.jpg)
.jpg)
それでは、管理職になりたくない3つの回答とそれぞれの具体的な内容について論破していきます。
論破①:管理職に向いていない?→実は一番の適性がある!
「管理職になるにはストレス耐性が高く、視野の広い人間でなければならない」
「すべての業務に長けている必要がある」
現代の管理職に一番必要な要素は、能力の前に「謙虚」さです。
驕らずに周囲の意見を取り入れ、学ぶ姿勢を持ち続けることができる。
そんな人は部下からの信頼を得て、組織を円滑に動かせるのです。
能力は後から伸ばせても、性格は簡単に変えられません。
「謙虚にして驕らず、さらに努力を」 稲盛和夫氏(稲盛ライブラリー)
つまり「管理職に向いていない」と思う人ほど、実は管理職に向いているのです!
出世欲、金銭欲がない
出世やお金のために仕事をする時代は、すでに終わりつつあります。今、重要なことは「自分の適性や経験を活かせる職務かどうか」です。
出世やお金は後からついてきます。
今の職務を続けたい
変化をせず「今のまま」に安心を感じることは自然なことです。もしかしたら、漠然と変化を恐れ、管理職を避けるためというのが本音かもしれません。
まずは管理職のことをよく知った上で、自分自身のキャリアについてよく考えてみてください。
今の上司に魅力を感じない
「こんな上司ならもっと尊敬できるのに」と思ったら、それがあなたが目指すべき管理職像でなのです。
上司をみて魅力を感じない人は、良い管理職になれる素質があります。
論破②:仕事量や仕事時間が増える?→それは「管理の仕方」の問題!
「管理職は仕事量が多く、自由な時間が無くなる」
「プレイヤーの仕事に加えて、部下の管理までやらなければならない」
それは本来の管理職の役割からすれば間違っていると言わざるを得ません。
管理職が仕事に追われる主な理由は以下の通りです。
- 部下の育成がうまくできていない
- 部下に適切な指示を出せていない
- 部下のストレスを気にしすぎて、仕事を振れない
結果、自分が抱え込むことに
優秀な管理職ほど、自分がいなくても組織が回る状態を作っています。
それは適切にマネジメントをして部下を活かしているからです。
「どんなに良い看護を充分に行ったとしても、ひとつのことーつまり小管理ーが欠けていれば、言い換えれば「あなたがそこにいるとき自分がすることを、あなたがそこにいないときにも行われるように対処する方法」を知らないならば、その結果は、全てが台無しになったり、まるで逆効果になってしてしまうであろう。
フローレンス・ナイチンゲール「看護覚え書ー看護であること、看護でないことー(改訳第7版)」現代社
「管理職=仕事が多い」は正確ではありません。
適切なマネジメントができれば、管理職はむしろ自由度が高い立場です。
割に合わない?/給与が上がらない?
厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査では、男性の非役職者の平均賃金が301千円に対して、課長級で495.6千円と、その差は約1.65倍です。
年間では差額2,335.2千円、仮に10年間続くと23,352千円!無視できない金額です。
さらに言えば、管理職の価値は給与だけで測れません。
- マネジメント次第で、働く時間を短縮しつつ、チーム全体の成果を最大化できる裁量を持つ
- 氷河期世代の管理職は世の中に不足しており、転職市場での価値が高い
実は長期的にみると、管理職になったほうが「割に合う」のです。
ストレスを避けたい?
管理職はストレスが多いと言われますが、一般職でもストレスはあります。
もし「言われたことだけやっていれば楽」だから管理職になりたくないのであれば、一般職の方がストレスの多い状況に置かれるかもしれません。ITやAI技術の台頭で、「言われたことをやるだけの仕事」ほど真っ先に淘汰されるリスクがあるからです。
ストレスを避けるより、上手に解消するスキルを身につける方が建設的です。
「ストレスに振り回される」のではなく、「ストレスとうまく付き合う力」を身につけましょう!



ストレスが「管理職>一般職」は勘違いです。役職に限らず、うまくストレスを逃がしましょう。下のリンクも参考にどうぞ。
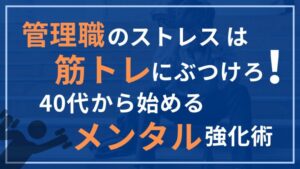
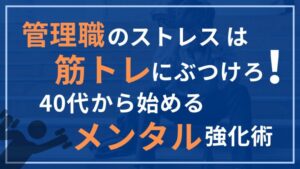


論破③:責任の重い仕事をしたくない? → 責任は抱えずに流す!
「管理職は責任が重い。だからなりたくない」
「一般職は責任が軽いから気楽」
責任に「重い・軽い」は確かにありますが、少なくとも会社員として働く上では「広い・狭い」があるだけです。
つまり、責任の範囲が「自分の仕事の範囲内」か「チーム全体」か、です。
管理職でも一般職でも、業務に対する責任の重さに違いはありません。
むしろ、管理職は責任を上に伝達する役割が重要であり、自分自身に責任がかかることは案外少ないものです。
経営学者のヘンリー・ミンツバーグは自身のマネジメントの定義として、主に「対人関係」「情報伝達」「意思決定」の3つに分類できるとし、その3つの活動からさらに、3つの対人関係の役割、3つの情報関係の役割、4つの意思決定関係の計10の役割があるとしています。
現代の管理職はこの3つの活動の中でも、特に「情報伝達」の部分が重要になっています。
サラリーマンである以上、社長以外は全員「中間管理職」 です。
適切なマネジメントができれば、ストレスの流れを調整し、自分だけが負担を抱え込むことを防ぐことができます。
割に合わない
すでに登場した「割に合わない」よりも、精神的な面に着目した内容になります。
ドライに聞こえるかもしれませんが、個別の業務の責任は部下にある と考えるべきです。もちろん、教育や役割分担が不十分であれば、避けられるはずのトラブルも発生します。しかし、マネジメントに100点はなく、たとえ完璧に仕事をしてもトラブルは起こるものです。
だからこそ、管理職が最も重視すべきは「責任の正しい流れを作ること」。責任が生じるトラブルほど、組織内で速やかに正確な情報共有を行うことが重要 なのです。
客観的に見れば、全体像が見えない一般職の方が「割に合わない」かもしれません。
ストレスを避けたい
繰り返しになりますが、ストレスは避けるものではなく、消化するもの。
さらに言えば、管理職はストレスの元である責任を適切に流すことができるポジションです。むしろ責任をため込む管理職こそ、言い方は悪いですが組織にとってさらなるストレスの要因となりかねません。
「管理職=責任」という先入観をすてましょう。



自分の尻は自分で拭け!みたいな考えは古いです。みんなで尻を拭くためにティッシュを配る=ストレス分散が今は重要です。
まとめ:”管理職は罰ゲーム”を完全論破!やり方次第で最強ポジション説
ここまで「管理職は罰ゲーム」と言われる3つの理由とその誤解について論破してきました。
この記事で伝えたかったのは、次の3点です。
- 「管理職は罰ゲーム」というのは誤解であり、正しく理解すればむしろ魅力的なポジションである。
- 管理職の責任は「重い・軽い」ではなく「広い・狭い」。適切に責任を流すことで、負担をコントロールできる。
- 管理職の仕事量やストレスは、マネジメント次第で大きく変わる。適切なマネジメントを身につければ、むしろ自由度が高まる。
そして、この記事を書いた最大の理由は、今、管理職として奮闘している方々に勇気を持ってもらいたい からです。
一部のネガティブな声が目立っていますが、実際の職場には、やる気のある若手もいますし、会社を良くしようと努力している管理職もいます。
だからこそ、管理職という職務に誇りを持ち、前向きに取り組んでほしい。
この記事が少しでも、その助けになれば幸いです。

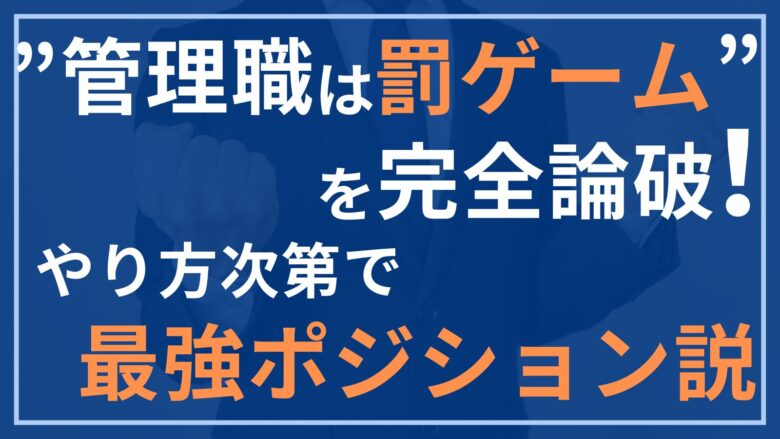
-300x169.jpg)




コメント