「飲みにケーション」と聞くと、どんなイメージを持ちますか?
「不要」「うざい」「おじさん」——実際に検索すると、ネガティブな言葉が並びます。
結論から言うと、今の時代に無理をして「飲みにケーション」をする必要はありません。
部下との関係を深めるために飲みに行くより、管理職も自分の時間を大切にしましょう。
今の若い世代は、仕事とプライベートを切り分ける傾向が強く、飲み会よりも職場での協力関係を重視しています。
むしろ、一緒に仕事をして成功体験を積み上げるほうが、はるかに良い信頼関係を築くことができます。
飲み会の席でのアルハラやパワハラが当たり前、そんな時代を経験してきた氷河期世代の管理職だからこそ、今の変化を誰よりも理解できるはずです。
ここでは、「飲みにケーション」が時代遅れになった理由と、現代の管理職が部下との信頼関係を築く方法をお伝えします。
最後まで読み終えていただければ、無理して「飲みにケーション」をする必要はないことがわかります。
 TAKA
TAKA上司も部下も無理して行きたくないのに、なぜか行かなきゃいけない雰囲気がありますよね。
「飲みにケーション」とは?昔と今で変わった役割
「飲みにケーション」は「飲み」+「コミュニケーション」の造語です。
お酒の場での会話を通じて、仕事関係者との関係を深める文化を指します。
かつて、仕事の延長としての飲み会には、次のような目的がありました。
- 関係性の構築(普段の業務では話せない本音を聞き、信頼関係を築く)
- 人物の評価(仕事中とは異なる一面を知ることで、性格や価値観を把握)
- 過去からの習慣(自分も上司に連れて行かれた経験があり、それを引き継ぐ文化)
今はチームワークが重視されるため、職場はコミュニケーションを取りやすい雰囲気が前提です。
しかし、かつては仕事中は業務に集中し、人間関係は夜の飲み会で深めるというのが定番でした。
そのため、職場の雰囲気や人間関係はお酒の場で作られ、部下の性格やプライベートを知る数少ない機会になっていました。
さらに評価基準が今のように明確化していなかったため、「お酒の席での印象」が人事評価に影響することも珍しくありませんでした。
そして最も大きな要因は「上司もまた、かつて飲みに連れ出されていた」ことです。



私も頻繁に付き合わされました。上司の自慢話を聞くのがメインでしたね・・・
しかしコロナ禍を転機に、大人数の飲み会ができない状況となり、会社の飲み会を見直す流れが加速しました。
リモートワークの普及もあり、「仕事の関係は業務内で完結させる」という価値観が広がったのです。
実際に、産労総合研究所の調査では、「職場の飲み会は参加したいか?」という問いに、約70%が否定的な回答をしました。
つまり、現代のビジネスパーソンの多くが職場の飲み会に魅力を感じていないのです。
職場での飲み会は、もはや役目を終えつつあると言えるでしょう。
「飲みにケーション」が時代遅れと言われる3つの理由
飲み会に頼らず関係性を構築していくためには、まずは「飲みにケーション」がなぜ避けられるようになったのかを知る必要があります。
主には3つの理由があります。
- ワークライフバランスの変化
- 飲酒人口の減少
- 金銭的に余裕がない
理由1:ワークライフバランスの変化
Job総研による「2023年ワークライフ実態調査」によると、特に若い世代ほどプライベートの時間を重視する結果となっています。
また同調査では、73%の人がワークライフバランスが「仕事のモチベーション」に影響すると回答しています。
つまり「飲みに行かないから仕事に後ろ向き」ではなく、良い仕事をするためにプライベートを充実させたいのです。
理由2:飲酒人口の減少
昔は「タダ酒が飲めるなら」と、上司に誘われれば付いていく部下も少なくありませんでした。
しかし、現在はお酒を飲む人自体が減っています。
厚生労働省の調査では、週に3回以上飲酒する男性は1989年51.5%から2019年33.9%に低下しています。
またストレスの発散方法も変化しています。
コロナ禍を経て「飲み会に行く」よりも「睡眠・休息」や「身体を動かす」といった健康的な行動が増加しているのです。
チューリッヒ生命の調査において、コロナ禍で始めたストレス発散方法の回答では「身体を動かす」が8.4%でトップとなっています。
実際、私もコロナ禍直前に筋トレにハマり、今ではお酒を飲みたいと思わなくなりました。
一度健康に気を使いだすと、お酒を飲む機会は自然と減るものです。
お酒を飲まない人、飲む習慣のない人を、飲み会に誘っても当然良い効果は望めません。
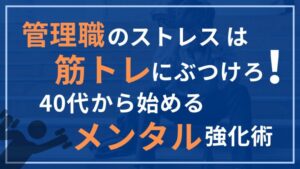
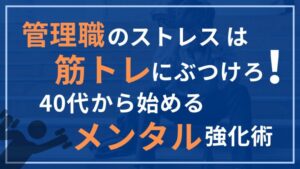
理由3:金銭的に余裕がない
これは、管理職側の問題です。
最近のニュースでも報道されていますが、企業は優秀な人材を雇用するために初任給を大幅に上げています。
一方で、管理職の給与上昇は抑えられているのが現実です。
厚生労働省の2023年賃金増減率の調査では、新卒者の賃金は3.9%増に対して、課長級はわずか0.8増にとどまっています。
また、管理職の中心世代である40代は家庭にお金がかかる時期でもあり、自由に使えるお金はさらに少なくなります。
この話題では若い人の理由が協調されがちですが、管理職側にこそ避ける傾向が強くなっています。
双方ともに避ける傾向が強くなれば「飲みにケーション」が絶滅するのは時間の問題かもしれません。



金銭面だけでなく、ハラスメントに神経質な現状を考えると、正直リスクが上回っていると思ってしまいますよね。
「飲みにケーション」なしでも部下と信頼関係を気付く方法
たとえ「飲みにケーション」をしないとしても、チームとして個々の関係性を向上させる必要があります。
ここでは、その方法について見ていきましょう。
仕事で共通の体験を持つ
仕事の関係性は業務時間内に構築するのが一般的になっています。
そのためには単に個々が業務をこなすだけではなく、共有の体験を持つことが重要です。
たとえば、業務の改善のアドバイスをしたり、問題の解決の背中を押したりすることで、信頼関係が深まります。
昔のように「見て覚えろ」「自分で考えろ」の時代は終わりました。
若い世代とは惜しみなく会話をして、積極的にコミュニケーションを取りましょう。
今の管理職に求められるのは、一方通行ではなく部下と一緒に成長していく姿勢です。



一見すると当たり前のことですが、本当にできているか考えてみてください。「惜しみなく会話」できてますか?
テキストメッセージの活用
今はメール、LINE、SMSなどのテキストメッセージでのコミュニケーションが主流になっています。
相手と直接対面しないので精神的なプレッシャーが無い状態で連絡を取り合えます。
社内でチャットツールを導入する企業も増えていますが、中小企業ではまだ少数派です。
しかしプライベートではいまや電話よりも身近なツールになっています。
総務省の調査によると、LINEの利用率は10代から50代で90%以上、60代でも86.0%と非常に高い水準にあります。
これだけ普及しているツールですので、仕事でも活用すべきです。
たとえば私の場合、遅刻や休みの連絡、外出先から帰社時間の報告などにテキストメッセージを活用しています。
「体調大丈夫?」「家の方は平気?」といった何気ない言葉を添えると、そこから自然に会話が広がりますよ。



「休みの連絡はLINEでするな!」とか言ってませんか?こちらから敷居をぐっと下げてあげましょう。
ただし、業務上のデータや仕事の会話については機密情報もありますので十分注意してください。
例外的に飲み会もアリ?管理職が押さえるべきポイント


基本的に「飲みにケーション無し」が今後の主流ではありますが、関係を深める手段として食事が効果的なことに変わりはありません。
ただし、誘う側の管理職は以下のルールを守りましょう。
- 遅くとも2週間前には予定を決める(家庭での晩御飯の準備の支障にならない)
- 誘う人数は多くても3人まで(1人1人と話ができる人数)
- お金は管理職が負担(頻繁にやる必要はないので頑張って捻出しましょう)
- 最大2時間、お店1軒で帰る(2次会があるとしても部下だけで)
これは自分が楽しむための飲み会ではなく、部下への慰労会です。
できだけ参加メンバーに楽しんでもらい、気持ちよく会話をしてもらえるようにしましょう。



チームで飲むこと自体を否定しているわけではありません。リクリエーション以上の意味を持たせない意識が大切です。
専門サイトなどでは「ランチ」での関係作りがよく取り上げられますが、私はおすすめしません。
ランチも業務外の休憩時間であり、メンバーがリラックスするための貴重な時間です。
午前中の仕事を頑張った部下に、ゆっくりとお昼休みを取らせてあげてください。
氷河期世代の管理職こそ「飲みにケーション」否定派
ここで、あえて強調しますが、『飲みにケーション』に最も苦労した世代は、現在の40代、いわゆる氷河期世代です。
就職氷河期の厳しい競争を勝ち抜いても、職場では上司からの飲み会の誘いを断れず、飲みの席での説教や、無理な酒の強要に耐えるのが当たり前でした。
確かに、飲みの場だからこそできる会話もありましたが、それ以上にパワハラまがいの説教、上下関係の強制、断れない空気といった問題が多かったのも事実です。
だからこそ、私たち氷河期世代は、『飲みにケーション』の良い部分と悪い部分を身をもって知っています。
『飲みにケーション』の問題の本質は、単なる世代間のギャップではありません。
コンプライアンスの意識が強まり、リモートワークや個人の価値観が尊重される時代になり、飲みにケーションは自然と衰退していったのです。
だからこそ、飲みにケーションの負の側面を経験した私たち氷河期世代の管理職が、率先して新しい関係構築の形を示す必要があります。
私たちの世代が過去に受けた飲み会文化の負の遺産を、次の世代に押し付けるのはもう終わりにしましょう。



せっかく管理職になったんですから、頑張りましょう!
ストレスはうまく逃がしてくださいね。


まとめ:これからの管理職に必要なコミュニケーションとは
かつて「飲みにケーション」は職場の人間関係を築く重要な手段でしたが、時代とともに価値観が変化し、今では必ずしも必要ではなくなっています。
本記事では、以下の3つのポイントを解説しました。
- 「飲みにケーション」が時代遅れと言われる理由
- ワークライフバランスの変化
- 飲酒人口の減少
- 管理職の収入が伸び悩み、飲み会の負担が難しくなった
✔ 「飲みにケーション」なしでも部下と信頼関係を築く方法
- 仕事を通じて共通の体験を持つ
- テキストメッセージを活用する
- 今の時代にあった食事の誘い方を心掛ける
✔ 氷河期世代の管理職こそ「飲みにケーション」から卒業すべき理由
- 過去のアルハラ・パワハラの経験から、飲み会の負の側面を理解している
- 若手だけでなく、管理職も飲み会を避ける傾向が強くなっている
「飲みにケーションがないと本音が聞けない」という固定観念を捨て、時代に合ったコミュニケーション が必要とされています。昔のように、管理職がストレス発散に部下を連れ出すことがないように、別の方法でストレス発散しましょう。


-300x169.jpg)
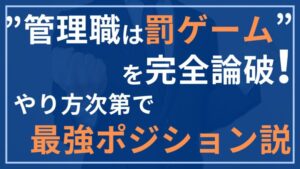



コメント