「元の上司が部下になる」
この状況に直面したとき、事前にわかっていたとしても多くの管理職が戸惑いやストレスを感じることでしょう。
かつて指示を受けていた相手が、今は自分の指示に従う立場になる——
定年延長が常態化した今、このようなケースは当たり前の景色になりつつあります。
とはいえ、この関係性を正しく受け入れることは簡単ではありません。
この記事では、負担の主な原因を掘り下げ、気まずさを解消するための理解を深めていきます。
 TAKA
TAKA大企業だと管理職経験者にそれなりのポストが用意されていますが、中小企業だと現場に戻ってくるので逃げ場がないんですよね。
年上の元上司が部下になるとき、なぜ心理的負担が生じるのか?
原因①:関係性の変化がもたらす「役割のズレ」
心理的負担の大きな原因は、過去の上下関係と現在の役割がズレていることです。
以前の「上司—部下」という固定観念が、現状の「管理職—部下」という関係にうまく適応できないことで、ストレスを引き起こします。
日本の職場文化では、年功序列や上下関係が根強く、役割の変化に適応するのは簡単ではありません。
特に、過去の関係性に基づく思い込みが強いほど、このズレが心理的負担を増幅させます。
原因②:年齢による「立場のプライド」が負担に拍車をかける
年上の部下という状況は、相手のプライドが影響し、関係を複雑化させます。
感覚的に、ある程度年齢が高くなるとプライドが高くなる傾向にあると感じているのではないでしょうか。
学術的にも年齢とともに自尊心が高まることは調査結果で明らかになっています。
東京理科大学理学部第二部教養の荻原祐二嘱託助教と京都大学大学院教育学研究科の楠見孝教授は、青年期から老年期における自尊心の年齢差について大規模な調査を実施し、年齢が高い人ほど自尊心が高いことを解明しました。
経験やキャリアに対する自尊心が強くなり、部下という立場に葛藤を抱きやすくなります。
これはその人の性格のみに由来した話ではないため、年齢とともに醸成されたプライドは「管理」や「指導」で簡単に矯正されません。
このことを理解せず、相手のプライドに配慮のない対応を行うことは、関係悪化の大きな原因となります。
原因③:自分自身の「上司否定」の思いが心理的負担を生む
自分の中にある「上司への否定的な思い」が、心理的負担を生む原因になります。
部下だった頃に感じていた「上司への不満」や「自分ならこうする」という考えが、管理職になった際に無意識の行動として表面化します。
これにより、元上司を否定する形で振る舞ってしまい、自分自身の心理的負担を増やす結果となります。
カール・ユングが提唱した「シャドウ」の概念では、無意識に抱えている自己の一部を他者に投影することで対立や葛藤が生まれるとされています。
この投影が元上司への否定的な態度を引き起こし、後から自己否定感や罪悪感を生じさせるのです。
上下関係ではなく役割分担!関係性と心を保つマインドセット3点


管理職に昇進したとき、私たちは「上下関係」という枠組みで物事を捉えがちです。
しかし、現代の職場では「上下」という概念だけで人間関係を整理するのは難しくなっています。
特に年上の元上司が部下になる状況では、組織上の立場とキャリアのバランスを意識することが不可欠です。
次に、元上司との関係性とあなたの心をを保つためのマインドセットを3点紹介します。
- 元上司との関係は、「プライスマイナスゼロ」と考える
- 管理職は「上下の上」ではなく部下を管理・支援する「役割の担い手」
- 元上司の得意な仕事を任せて「適材適所」でコントロールする
元上司との関係は、「プライスマイナスゼロ」と考える
組織上の立場では上でもキャリアや年齢では元上司が上です。この関係を「プライスマイナスゼロ」と考えましょう。
年齢やキャリアを尊重する姿勢を示すことで、元上司が安心して新しい役割を果たせるようになります。
管理職は「上下の上」ではなく部下を管理・支援する「役割の担い手」
管理職とは「役割」の呼称であり、人の上に立つわけでは無い、と考えましょう。
現代の職場では、前線で働く部下を尊重し、チーム全体の調和と成果を出せる環境を作ることが求められています。
元上司の得意な仕事を任せて「適材適所」でコントロールする
元上司には業務の範囲を明確にし、なるべく得意な役割を与えることで、自発的に力を発揮してもらう環境を作ることが効果的です。
フラットな評価を意識して、他の若い担当者と同じ土俵で勝負させることは自尊心を傷つけるだけです。
はっきり言ってしまえば、「特別扱い」をしてあげるということです。そのためには他の若い部下に対しては事情を説明して理解を得ておく必要があります。若い部下にとって元上司は祖父に近い世代差があるので、私たちが思うより寛容に受け入れてくれます。



納得いかないかもしれませんが、これが一番現実的です。
「いつか自分も通る(かもしれない)道」と割り切りましょう。
元上司の部下に対して私が実践した3つの行動


私自身の元上司との管理職交代劇は、かなり後味の悪い形でした。
年齢とともに自己保身的な行動が目立つようになり、当時中間管理職だった私とぶつかることが増えました。
それを見かねた社長が半ば強引に私を引き上げて、元上司を部下へと格下げしたのです。
お互いの感情は最悪でしたが、部署運営のために次のような行動を心がけました。
行動①:若い部下との徹底的な意識共有
若い部下には元上司以外との関係性を隠さず話し、これからの課題を意識共有しました。
元上司を気にするあまり、つい元上司との関係性ばかり意識してしまいそうですが、本当に大切するべきは未来ある若い部下との関係性です。
元上司を「特別扱い」するための下地作りを丁寧に行いましょう。
現代の管理職と部下の関係は、上下ではなく対等の意識が必要です。弱い部分も含めて「共有」することを大切にしました。
行動②:元上司の部下には指示ではなく相談スタイル
「~の件なんですけど、どう思いますか?」という相談スタイルを心がけました。
これは普通の部下にも同じことが言えるのですが、理解を得られないままの指示は結果に結びつきにくいです。
特に指示を受けることに慣れていない元上司の部下に対しては、会話の中で「自発的に」本人が言ったことになるよう仕向けました。



最初はうまくいかなくて、大変でした。
あまり結論を意識せず情報交換のつもりでやると良かったです。
行動③:必要以上に干渉しない
元上司の部下と方向性だけ合わせたら、それ以上のことは必要以上に干渉しないようにしました。
キャリアのある人に対して、結果が出る前から口を挟むことは自尊心を傷つけることになります。
もしうまく結果が出ない場合でも、「以前結果が良かった時はどんな状況だったんですか?」と過去の成功例を聞くようにしました。
元上司の肯定感を高めると同時に、私自身の引き出しを増やすことにも繋げました。
若い部下と、年齢の離れた元上司の相性が意外に良いことに助けられた面もあります。時にはチームメンバーを信頼して見守ることも大切だと痛感しました。



とはいえ、何かあれば全て自分の責任です。目に見えないストレスが若い部下にかかってないか、かなり留意しました。
管理職が心の余裕をつくるための方法3選
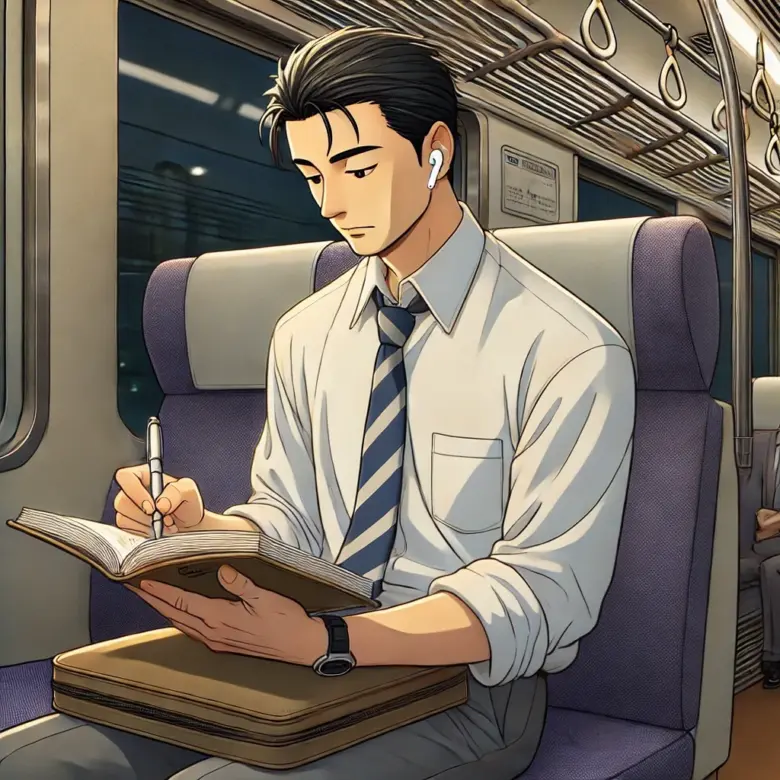
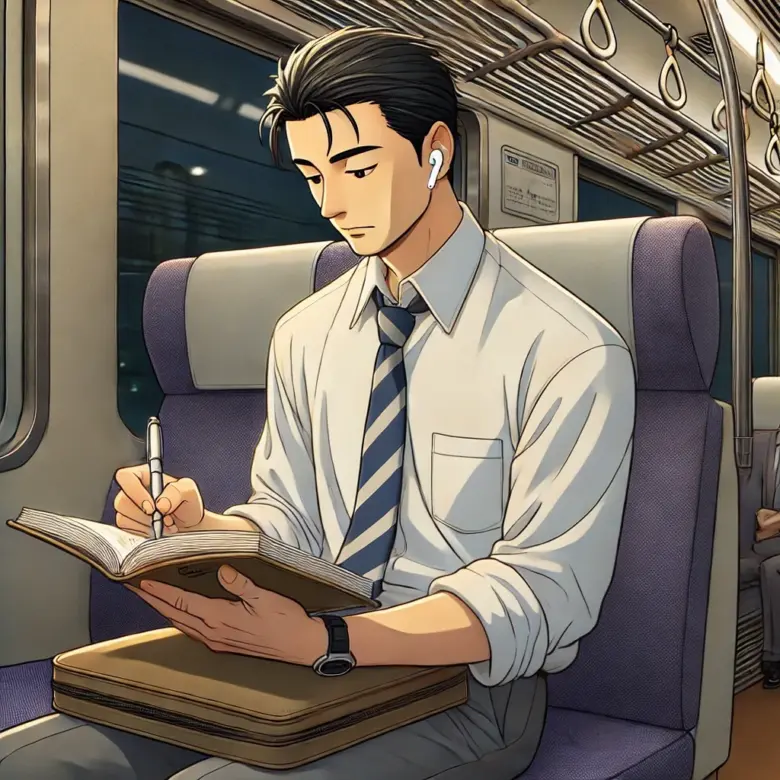
そもそも管理職になったばかりの頃は、自信と不安を交互に感じる時期でもあり、特にストレスが強くかかる時期でもあります。
そこに元上司との立場の逆転現象があれば、なおさら心の余裕を失うことにもつながります。
ここでは管理職を務めるうえで、私が実践した「心の余裕」を得るための方法を3つ紹介します。
- 独立開業できる資格を取得して、「人生の保険」を手に入れる。
- 少額でも構わないので副業で稼ぎを得て「会社以外の生き方」を知る。
- 筋トレで「生物的な強さ」を得る。
大切なのは会社に依存しすぎないことです。
会社側の視点で言えば、その会社でしか生きられない人材は評価を得られない時代になっています。
目の前の仕事に集中するために、逃げ道を用意しておきましょう。
私の元上司は将来の不安から保身的な行動が目立つようになり、結果的に部下の信用を失いました。会社以外で生きる強さを手に入れることは、会社への不義理な行動では決してありません。



実際に全て実践した結果、会社の評価は上がりました。その頃には元上司との立場の逆転なんて全く気にならなくなりました(笑)


まとめ:元上司が部下に!管理職が意識すべき3つのポイント
この記事を大事な部分をまとめます。
- 現在の「役割」に集中する
過去の上下関係ではなく、現在の役割分担に目を向けましょう。得意分野を活かして適材適所を意識することが大切です。 - プライドへの配慮を忘れない
年齢やキャリアによるプライドを尊重し、「相談スタイル」のコミュニケーションで自発的な行動を促しましょう。 - 自分の「余裕」を保つ
資格取得や副業、筋トレなどで心の余裕を作り、冷静な判断力を高めましょう。
元上司が部下になる状況は、最初は戸惑うかもしれませんが、適切な対応を心がけることで関係を良好に保てます。
ポイントを実践し、管理職としての役割を前向きに楽しんでください。


-300x169.jpg)
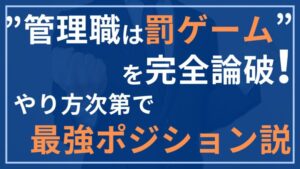


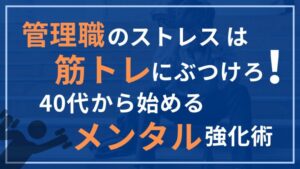

コメント