現代の管理職にのしかかる様々なストレスに強くなるために、筋トレが非常に効果的です。
なぜなら「筋トレ」には単純にストレス発散以外にも、仕事をしていく上での様々な恩恵があるからです。
ここでは私自身が実践した内容をもとに、ストレスと戦う40代以上の管理職に向けて、筋トレの効果と実践方法をお伝えします。
この記事を読んでいただければ、管理職にとって「筋トレ」が有効でること、そして40代以上が本当に行うべき「筋トレ」の内容がわかります。
ストレスの多い管理職が筋トレをすべき3つのメリット
筋トレには単純に運動してのストレス発散効果以外にも、副次的な効果として3つのメリットがあります。
- 自分に自信が付くことによるストレス耐性アップ
- 見た目が良いと周りの見方も変わる
- 趣味として人の評価を得やすい
メリット1:自分に自信が付くことによるストレス耐性アップ
筋トレは外見、そして内面から自分に自信を付けることができます。
そして自信は自分をストレスから守る壁となってくれます。
具体的には以下の効果により自信に繋がります。
外見上の効果
筋トレを継続して行っていると、自然と姿勢が良くなります。
具体的には背筋を伸ばし胸を張るといった「自信のある姿勢」を取ることで自己評価や自己肯定感が高まります。
この自信のある姿勢は「パワーポーズ」と呼ばれ、やる気や自信につながる男性ホルモンのテストステロンが増加するという研究結果が、ハーバード大学のエイミー・カディ教授らにより示されています。
内面の効果
筋肉を増やすためには、自分の限界を少しだけ超えた重量や回数で自分を追い込む必要があります。
そのトレーニングは自らの肉体と精神にストレスを掛け、それを少しずつ乗り越えることを繰り返します。
複数の研究によれば、ストレスを受けた経験や、それを乗り越えた経験を積み重ねることで、ストレス対処スキルが向上するとされています。
つまり筋トレによって内面的にもストレスに強くなります。
メリット2:見た目が良いと周りの見方もかわる
筋トレを行うことでスタイルが良くなり、周りの評価が変わります。
たとえば、ビール腹の上司よりも、お腹のすっきりした上司の方が当然部下の受ける印象が違いますよね。
「人は見た目が9割」という言葉もありますので、自己肯定感を高めるために筋トレでスタイルを整えることは大変効果的です。
「人は見た目が9割」
竹内一郎氏のベストセラーである『人は見た目が9割』は、コミュニケーションや人間関係において、視覚的な情報がどれほど重要かを解説した一冊です。社会に出れば見た目で判断しないようにしようと誰もが意識しますが、それこそ筆者の主張を裏付けているのだと実感します。
メリット3:趣味として人の評価を得られやすい
筋トレはこの10年程度で大きく普及し、市民権を得たスポーツです。
たとえば、笹川スポーツ財団の調査によれば年に1回以上筋トレを行う人の推計人口は2000年の役726万人から2022年には約1,640万人と2倍以上に増加しています。
一方、昔のサラリーマンの定番スポーツと言えばゴルフでしたが、時間やお金のかかることから若い人を中心に敬遠される傾向にあります。
これらのことから、筋トレは趣味として話題に出しやすいスポーツになったと言えます。
 TAKA
TAKA私は人に話せる趣味が少ないので、「筋トレ」はビジネスでの雑談では鉄板ネタになってます。
焦りがケガの元!40代管理職が筋トレで避けるべき落とし穴


筋トレは継続することで大きなメリットをもたらしますが、間違った方法や無理をすれば新たなストレスの原因となりかねません。
焦らずステップバイステップで進めることが、健康的に長く続けるための秘訣です。
ここでは、ケガを防ぐために必要なポイントを解説します。
注意すべき点1: 筋肉の成長には時間がかかる
筋肉はいきなり肥大するわけではありません。
まずは神経系からの適応が始まり、実際に筋肉が増えるのには1年以上かかることを見据えるべきです。
短期間で結果を出そうとすれば、ケガや身体への負担が増すだけです。
週に2~3回、無理のない重量から始めて徐々に増やすのがベストです。
注意すべき点2.:インフルエンサーの方法をそのまま真似しない
SNSやYouTubeには魅力的なトレーニング動画が溢れていますが、上級者の内容をそのまま実践するのは危険です。
彼らの体は長年の努力と特別な環境によって作られたものであり、初心者には不向きなメニューも多いのです。
まずは初心者向けと銘打った内容を参考に基礎を固めましょう。責任世代である40代以上の管理職が、筋トレでケガをすることだけは絶対に避けなければいけません。
注意すべき点3: 楽しむことを忘れない
筋トレをストイックに捉えすぎると、継続が難しくなります。
小さな成功体験を積み重ね、達成感を味わいながら続けることが重要です。
筋トレの指標は回数や重量だけではありません。「きれいなフォーム」で行うことや、「健康診断の結果」など自分なりの指標で楽しんでいきましょう。
筋トレは、健康とストレス解消に大きなメリットをもたらしますが、無理をすると新たなストレスを抱えるリスクも伴います。
焦らずじっくり取り組むことで、長期的な効果が得られるのです。
小さな変化を楽しみながら、無理なく続けていきましょう!



自分の筋トレを動画にとって、きれいなフォームを追求するのおすすめですよ。
今なぜ会社は健康な社員を評価するのか
筋トレをすることで健康になることは、会社の評価アップにもつながります。
管理職として会社の評価をしっかりと得ておくことは、部下からの評価にも良い効果を与えます。
それではなぜ、健康になることが会社の評価につながるのでしょうか。
それは近年企業に広まっている「健康経営」のという経営手法にあります。
健康な社員は、病欠のリスクが低く生産性が高いため、企業の成長に大きく貢献すると考えられています。
実際に健康経営の取り組みを行う企業の売上高成長率は平均よりも高い傾向にあります。
運動習慣者比率が10%高い企業は売上高成長率が0.34%高い(引用元:経済産業省調査)
また、筋トレや食事管理などの自己管理ができる社員は、仕事においても高い信頼を得やすいです。
さらに、健康であることは、医療費や離職率の低下といった企業のコスト削減にもつながります。
結果として、健康的な見た目や体型を持つ社員は、仕事の現場でも第一印象が良く、社内外からの評価もアップするのです。
会社での評価をあげることは管理職としての発言力を強めますので、結果的にストレス軽減にもつながります。



健康診断で引っかかる項目が全く無くなり、今や会社の若手より私の方が健康体です。
初心者が筋トレを始める2つのステップ【私の経験】
いざ筋トレを始めようと思っても、情報が多くて何から手を付ければよいかわかりません。
ですので、ここでは私の経験をもとに40代以上におすすめの筋トレ方法を紹介します。
筋トレを始める2つのステップ
まずは自宅でできる範囲のトレーニングから始めることをお勧めします。
もちろんジムには効率的なマシンがあり、他の人から刺激を受けるなど良い面もあります。
しかし、ジムに行くための時間まで捻出するとなると、それだけ筋トレのハードルが上がります。
一番優先すべきは忙しい管理職でも継続できる環境を整えることです。
筋トレの障壁を少しでも取り払うために、自宅でのトレーニングから始めましょう。
いきなりダンベルを買わなくても水を入れた2Lペットボトルでも構いません。
私はホームセンターで4㎏、6㎏のダンベルを買ってきました。
慣れるまではダンベルのトレーニングで十分ですし、実際に全身の筋肉を鍛えられます。
もし慣れてきたらダンベルの重量を増やしつつ、ベンチも買って効率を上げていきましょう。
実際に私が参考にした動画
初めて参考にした動画はこちら。コアラ小嵐氏の動画はエンタメ要素も多くておすすめ!
ベンチを買ってからはこちらも参考にしていました。katochan33氏は人柄もステキ!
筋トレに慣れてくると器具を増やしたくなりますが、正直なところストレス対策の目的であればダンベルで十分だと思いますよ。
ケガだけには注意をしてまずは楽しみながら続けることを目標にしましょう。



最初はダンベルを床に落として妻に怒られたりしました・・・
体が動きと重さに慣れるまでは絶対無理はしないで下さい。
まとめ:筋トレで管理職としての自分をアップデートしよう
現代の管理職が抱えるストレスは、仕事の責任や人間関係、健康への不安など多岐にわたります。
そんな中で、筋トレは単なるストレス発散にとどまらず、自信の向上、見た目の改善、健康的な生活習慣の定着といった多くのメリットをもたらします。
筋トレを通じて得た体力と精神力は、仕事の困難を乗り越える強い味方になります。
また、健康経営が浸透する今、健康であること自体が会社での評価アップに繋がるため、筋トレはキャリア形成の一環とも言えるでしょう。
40代以上の管理職だからこそ、無理せずステップバイステップで進めることが大切です。
まずは自宅でできる簡単なトレーニングから始め、日々の成長を楽しむことを意識してみてください。
継続することで、ストレスへの耐性と管理職としての自信を同時に手に入れることができますよ。
「筋トレで変わるのは身体だけではない」という言葉を胸に、今日から少しずつ始めてみませんか?

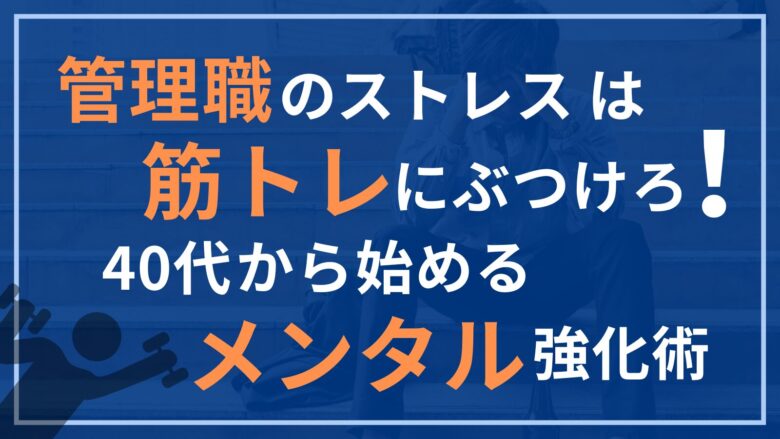

-300x169.jpg)
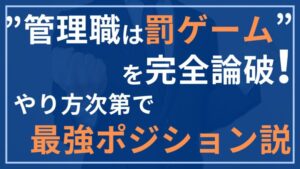




コメント